私は、電機関連の製造業で品質管理や設備保全に長年従事し、60歳で定年退職を迎えます。
雇用延長制度はあるものの、これまでと変わらぬ業務負荷に「このまま消耗するだけなのか?」
しかも給与は大幅に減少します。それに雇用延長は65歳で終了します。
そんな中、昔の上司から「電験三種に挑戦してみたら?」と勧められたことが転機になりました。
調べてみると、電験三種は電気設備の保守・監督を担う国家資格で、再生可能エネルギーや省エネの現場でも重宝される人気の資格であることを知ります。かなりの難易度ですが、自分の将来の自由度を広げることができるのは大きな魅力です。
56歳から猛勉強をいして58歳で2回目の試験で4科目合格を達成。働きながらの挑戦でしたが、現場経験と照らし合わせながら学ぶことで、知識が自分のものになっていきました。資格は失効せず、生涯有効。しかし、現場で活躍し続けるには「実務力の継続」と「信頼の積み重ね」が不可欠だと実感します。
あと2ヶ月で60歳定年という時期ですが、転職活動を開始。転職エージェントの支援を受けながら、電験三種を活かせる会社を探し、面接対策や条件交渉も含めて伴走してもらっています。
私は、70歳まで現場に立ち続ける「生涯現役の技術者」を目指し、若手への知識継承、安全文化の定着、設備の長期信頼性確保に貢献することを志しています。
定年を前に、立ち止まって考えた
もう直ぐ定年。フィールドサービスの再発防止担当で、不具合は絶えず発生し、多忙な日々が続きます。不具合が起こる原因は、製品設計の問題も多く、旧機種では、フィールドサービス技術員が参考にする保守説明書も準備されていません。そのため、一部の技術員は、不具合発生は、自分に原因があるとは思っていません。そのような状況だと有効な再発防止策も出るものではありません。
「このままあと5年間、強いストレスに耐えながら消耗するだけなのか?」
そんな疑問と不安が頭をよぎりました。
しかし、私には、昨年取得した第3種電気主任技術者資格があります。
今こそ、この資格を利用しない手はありません。
4年前の上司の一言が転機に
4年前には、環境推進業務に携わっていました。その時の上司からこう言われました。
「君の理論的な思考をみていると、電験三種、いけるんじゃないか?受けてみたら?」
そのときは、電験三種って聞いたこともありませんでした。
調べてみると、電験三種は正式には第3種電気主任技術者資格で、電気設備の保守・監督を担う国家資格。発電所や工場、ビルなどの電気設備の安全運用に必要な資格で、再生可能エネルギーや省エネの現場でも重宝される“技術者の登竜門”でした。
ただし、合格率は10%前後。 理論・電力・機械・法規の4科目を突破する必要があり、働きながらの挑戦には相応の覚悟が求められます。
試験準備の本を開いた瞬間、私は思いました。
「これは、ただの資格じゃない。電気を扱う技術者として、電気・機械をより深く理解するため必要な学びだ。これを理解することは、電気を扱う人の責任とも言えるのでは!」
回路図、電磁気、発電方式、保安規定——ページをめくるたびに、自分が感じていた電気に対する不十分な理解で”もやもや”としてボンヤリしていたことが、はっきりと輪郭を表していくような感覚がありました。
資格取得は“始まり”だった
私は、品質管理や設備保守サービスの管理で20年以上働いてきました。
老朽化した機器、属人的な判断、曖昧な責任分担——そんな課題に向き合う中で、
「電力に関して、もっと根拠ある判断ができる技術者になりたい」
と強く思うようになりました。電験三種の知識により、その疑問の一部は解決してくれました。
この資格は、電力を使った社会インフラを守る知識を得た証であり、 「電気の現場で信頼される技術者になるためのスタートライン」に立つことができた証だと思いました。
働きながらの勉強は、決して楽ではありませんでした。 でも、毎晩少しずつテキストを開き、現場の経験と照らし合わせながら学ぶことで、知識が“自分の言葉”になっていきました。
電験三種(第三種電気主任技術者試験)は、以下の4科目で構成されています:
- 理論(電気回路、電磁気、電子回路など)
- 電力(発電・送電・変電・配電など)
- 機械(モーター、変圧器、パワーエレクトロニクスなど)
- 法規(電気事業法、技術基準、保安規定など)
この試験には「科目合格制度」があり、一度合格した科目は最大3年間有効です。
私は56歳から勉強を始め、1年半後の一回目の試験で、理論・電力・機械に合格、半年後の二回目の試験で法規を合格し、58歳で資格を取得しました。
再発防止推進などの実務とは直接関係のない分野でしたが、働きながらの挑戦で、思ったより早く、運良く合格することができました。
なぜ“生涯現役”を目指すのか
電気設備の保守・運用は、年齢を重ねても続けられる仕事です。むしろ、経験と知識がものを言う世界。私は、70歳まで現場に立ち続けることを目標にしています。
- 若手技術者に知識を伝える
- 安全と法令遵守を現場で根付かせる
- 長期的な設備信頼性を支える
こうした役割は、年齢に関係なく求められるものです。だからこそ、電験三種を取得し、「生涯現役の技術者」としての道を選びたいと思いました。
これからの挑戦
電気主任技術者の資格を持っていたら、60歳を超えていても、転職が可能と言われています。
これまでのストレスの強い職場から飛び出て、転職して長期に働ける可能性があります。
そのためには、転職エージェント会社に申し込み、担当者と連絡を取り合って、履歴書と職務経歴書を作成し、転職先の会社を紹介してもらい、書類選考の手続きをしてもらいます。そして、書類選考に合格したら、面接を受けることになります。
エージェントの担当者は親切で、連絡を取りながら履歴書・職務経歴書を整えてくれます。企業との面接に向けた準備を進めています。求人紹介だけでなく、面接対策や条件交渉まで伴走してくれる心強い存在です。
ストレスは強いものの雇用延長の選択肢もあるため、多少の心の余裕はあります。
しかし、今後、どのような面接をして、どのような条件を提示されていくのか、どのような苦労がまっているのかをレポートしていきたいと思います。

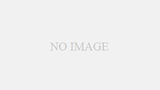

コメント